2009.10.20.
10/21-23と奈良で日本公衆衛生学会が催されます。
それに合わせて,日本衛生学会の理事会,衛生公衆衛生教育協議会がありました。
公衆衛生学会は,授業や日本血液学会の関係で参加できませんが・・・。日本衛生学会理事会には和文誌編集委員長として参加しないとならないので・・・
一日出張してきました。
    
会場は,奈良県文化会館でした。
  
せんとくん・・・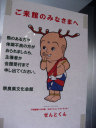
  
AMに理事会,午後後半が教育協議会でしたので・・
昼に散策・・・東大寺の方へ向かいました。
色づく街です・・・(南沙織の名曲,ご存じ?)
そして,奈良は,やはり古都です。
道路一本渡ると・・・その辺りは,タイムスリップな景色が広がります。
そして・・・正面に見えるお堂に向かったのですが,すでに東大寺の中の・・・戒檀堂でした。
大仏殿(金堂)の屋根も垣間見えます。
いにしえ・・・の雰囲気に浸ることができますね・・。
【54年(天平勝宝6)、聖武上皇は光明皇太后らとともに唐から渡来した鑑真(がんじん)から戒を授かり、翌年、日本初の正式な授戒の場として戒壇院を建立した。戒壇堂・講堂・僧坊・廻廊などを備えていたが、江戸時代までに3度火災で焼失、戒壇堂と千手堂だけが復興された。】
だそうです。
そのまま勧進所の裏手へ抜けて,大仏池(二ツ池)の方へ歩きます。
【1686年(貞享3)、露座のままだった大仏の修理、大仏殿の再建のため、公慶上人(こうけいしょうにん)は東大寺勧進所を建て、復興の寺務所とした。ここを拠点にして全国にくまなく行脚し、勧進に命をかけた。勧進所内には、同年建立の阿弥陀堂のほか、国宝僧形八幡神像を祀る。八幡殿や公慶上人を祀る公慶堂がある。】
池の辺りから,大仏殿の屋根も見えますね・・。
そのあたりから,正倉院の方へ向かいます。勿論,鹿もいますよ!
【正倉院(しょうそういん)は、奈良県奈良市の東大寺大仏殿の北西に位置する、高床の大規模な校倉造(あぜくらづくり)倉庫で、聖武天皇・光明皇后ゆかりの品をはじめとする、天平時代を中心とした多数の美術工芸品を収蔵していた施設。「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。元は東大寺の倉庫であったが、明治以降、国の管理下におかれ、内務省、農商務省と所管省庁は変遷し、1884年宮内省所管となった。第二次大戦後は宮内府を経て、現在は宮内庁の正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する施設等機関である正倉院事務所が管理している。正倉院の宝物には日本製品、中国(唐)や西域、遠くは
ペルシャなどからの輸入品を含めた絵画・書跡・金工・漆工・木工・刀剣・陶器・ガラス器・楽器・仮面など、古代の美術工芸の粋を集めた作品が多く残るほか、奈良時代の日本を知るうえで貴重な史料である正倉院文書(もんじょ)、東大寺大仏開眼法要に関わる歴史的な品や古代の薬品なども所蔵され、文化財の一大宝庫である。シルクロードの東の終点ともいわれる。】
ということで・・・今は宮内庁管轄です。確かに,東大寺のHPでも正倉院の説明はありませんね。
西と東の宝庫があって・・白壁の上にその瓦屋根が見えています。
やはりっていうか,小中学校の修学旅行生もたくさん・・・一緒に,正倉院を観に行きましょう。
校倉造は・・・社会の授業で何度も習いました。
さて,今度は南の方へ・・・広い木々と芝生の所・・・写生の人たちもたくさんいらっしゃいました。
結構,いつの間にか・・・足早に色付いている木々もあります。
秋ですね・・・もう。
この辺りは,講堂の跡だそうで・・その礎石の跡がありました。
 
大仏殿・・正面の中門の方へ・・西回廊の壁伝いに進みます。
 
そして,正面に回ると・・・やはり,とってもたくさんの観光客さんたちも・・・
外国人さんたちも・・・・。
大仏殿は・・福知山市立昭和小学校の修学旅行以来でしょうか・・。
  
向かいには鏡池があります。
〜〜〜〜〜〜〜〜
手向山八幡宮の方向っていうか,二月堂,三月堂の方へ少し進みましょう。
花まつり千僧法要記念宝塔や相輪がありました。
 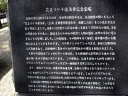  
   
大仏殿を後ろに眺めながら・・・・。修学旅行生に囲まれながら・・・。
そして,牡鹿の喧嘩を見ながら・・・。
八幡宮には行かずに,念仏堂〜鐘楼(大鐘)〜行基堂〜俊乗堂の方へ・・。
【鐘楼の北側に元禄年間、公慶上人が重源上人の遺徳を讃えて「俊乗堂」を建立。堂内中央に国宝「重源上人坐像」が安置されている。俊乗房重源は、1121年(治安元年)京都に生まれ、父は紀季重。13歳で醍醐寺に入って密教を学び、1167年(仁安2年)入宋し、翌年帰国。1180年(治承4年)平重衡によって大仏殿が焼かれるなど、東大寺の多くの伽藍が焼失したが、翌年60歳を過ぎた彼が造東大寺の大勧進職に任ぜられ、10数年の歳月をかけて東大寺の再興を成し遂げた。再建に当って、大仏様(だいぶつよう)と呼ぶ宋風建築様式を取り入れ、再建の功により大和尚の号を受け、1206年(健永元年)86歳で入滅した。】
  
本当に,大鐘 でs,
子供たち(たぶん,近くの)が,写生大会していました。皆,上手!
辛国社・・   を,横に階段を下りて行って・・・ を,横に階段を下りて行って・・・
また大仏殿の・・・今度は東回廊の外です。
長池・・・には,鯉の稚魚でしょうか・・・。
ぐるりと回って,大湯屋の方から・・・再び,俊乗堂の方へ・・向かいました。
子供たちは,まだまだ,写生の途中ですが・・。
そして,二月堂の方へ向かいます。。。
    
ここは開山堂
【開山良弁(ろうべん)僧正の像を祀るため、良弁堂ともよばれる。内陣中央に八角造の厨子がすえられ、国宝の僧正像が安置されている。良弁が遷化した宝亀4年(773)年から246年後に初めて御忌法要が行われたことから、この堂はその時に創建されたようである。】
三月堂

【東大寺建築のなかで最も古く、寺伝では東大寺創建以前にあった金鍾寺(きんしょうじ)の遺構とされる。752(天平勝宝4)の東大寺山堺四至図(さんかいしいしず)には「羂索堂(けんさくどう)」とあり、不空羂観音を本尊として祀るための堂である。旧暦3月に法華会(ほっけえ)が行われるようになり、法華堂、また三月堂ともよばれるようになった。もとは寄棟(よせむね)造りの正堂(しょうどう)と礼堂(らいどう)が軒を接して建つ配置であったが、鎌倉時代、礼堂を入母屋(いりもや)造りに改築して2棟をつないだ。正堂は天平初期の建築だが、礼堂は大仏様(だいぶつよう)の特色が見られる鎌倉時代の建築。時代の異なる建築が高い技術によって結ばれ、調和の取れた美しい姿を見せる。】
だそうです。
で,二月堂・・・お水取りでよくニュースで見ます。

【旧暦2月に「お水取り(修二会)」が行われることからこの名がある。二月堂は平重衡の兵火(1180年)、三好・松永の戦い(1567年)の2回の戦火には焼け残ったが、寛文7年(1667年)、お水取りの最中に失火で焼失し、2年後に再建されたのが現在の建物である。本尊は大観音(おおかんのん)、小観音(こがんのん)と呼ばれる2体の十一面観音像で、どちらも何人も見ることを許されない絶対秘仏である。建物は2005年12月、国宝に指定された。】
お参りしてみましょう・・・。
  
両脇に・・・神社もあります。南は飯道神社。
  
さて・・・縁側っていうのではなく翼廊っていうのかしら・・・舞台?? まで,進みます。
奈良盆地が一望です。
子供たちも・・・
さて,ぐるり・・と,回って北側には,遠敬神社・・・
その上には,山手観音堂もありますが・・・ここには誰も来ていなかった・・・。
大きな甍の屋根・・・やはり,そこには歴史の重さが・・・。
さて,下りて行きましょう・・・。
興成神社や,二月堂の参籠所,湯屋の脇を・・・北側の通路で,講堂跡地の方へ向かいましょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
こちらは,一般の住居もあるのでしょうか??
古の秋が,そこに見つかります。
 
僧侶の方が・・・紫の法衣で,ご年配ですが・・・可也高僧の方でしょうか?
 
勧進所の前を抜けます。
【1686年(貞享3)、露座のままだった大仏の修理、大仏殿の再建のため、公慶上人(こうけいしょうにん)は東大寺勧進所を建て、復興の寺務所とした。ここを拠点にして全国にくまなく行脚し、勧進に命をかけた。勧進所内には、同年建立の阿弥陀堂のほか、国宝僧形八幡神像を祀る。八幡殿や公慶上人を祀る公慶堂がある。】
さて,会議の時間が迫ってますので・・そのまま,再び,大仏池から・・・文化会館に戻りましょう!
|
![]()